今回は少しセンシティブな話題ですが、非常に大切なテーマを取り上げます。それは「コロナ関連給付金・補助金を巡る法人の詐欺事例」です。
新型コロナウイルスの影響で多くの事業者が経済的な打撃を受けました。政府や自治体は、それを救済するためにさまざまな給付金制度を設けました。持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金など…。
しかし、その制度の“善意”を逆手に取り、不正に給付金を申請し、結果として摘発される法人や経営者が後を絶ちません。
中には、最初は“軽い気持ち”や“知人に勧められた”程度だったというケースもあり、他人事では済まされない実態があります。
実際にあった法人関与の詐欺事例
たとえば滋賀県草津市の不動産会社。
代表者は自身の会社を使い、交際相手らと共謀して、20件にも及ぶ虚偽の申請を行いました。形式上は「個人事業主」として申請していましたが、申請に必要な書類はすべて偽造。結果、合計約2,000万円を不正に受け取っていたのです。
この件では、代表者に懲役4年6ヶ月の実刑判決が下されました。しかも、その交際相手や協力者にも有罪判決。
申請自体は簡単でも、国を欺くというのは重罪です。そして何より、“バレない”と思っていたのが大きな誤算だったようです。
元・経産省職員ですら関与
さらに驚くのは、制度の内側にいたはずの元経済産業省のキャリア職員が、複数名関与していた事件。
元職員2人は、知人名義で給付金や家賃支援金を虚偽申請し、合計で1,500万円以上を詐取。こちらも実刑判決が下されています。
つまり、給付金の制度に詳しい「プロ」すら手を染めてしまうほど、甘い誘惑があったということ。
一方で、制度の内容を知っていたからこそ、その「抜け道」も知っていたのだろうと思うと、非常に根が深いです。
「うちは関係ない」は本当?
中小企業の経営者の中には「うちはちゃんとやってるから大丈夫」と思っている方も多いと思います。
しかし、過去に実際に私のクライアントから、
- 「知り合いが給付金を受け取ったけど、売上減ってないのに通ったらしい」
- 「申請してくれる行政書士が、ちょっと調整してくれるって…」
といった“相談”や“報告”を受けたことがあります。
もちろん、私はその都度、「それは絶対にやめたほうがいいです」と伝えています。
なぜなら、悪気がなかったでは済まない世界だからです。
不正のリスクは想像以上に高い
では、不正受給が発覚した場合、どうなるのでしょうか?
よくあるケースでは以下のようなリスクがあります。
- 刑事罰(詐欺罪):10年以下の懲役刑の可能性。実刑判決も多い。
- 返還請求+延滞金:受給金額に対して3%〜20%の延滞金や加算金が課せられる。
- 信用失墜:社名が公表され、取引先・銀行との関係悪化。
- 倒産:資金繰りが立ち行かなくなり、倒産に至るケースも。
特に法人が関与したケースでは、代表者個人だけでなく、会社としての責任を問われる場合も多く、ダメージは計り知れません。
なぜ、こうした詐欺が起きるのか?
一番の理由は「制度が急ごしらえだった」こと。コロナ禍の初期、スピードが求められたため、審査が甘くなったのは事実です。
また、電子申請が可能だったため、書類もデジタル加工で簡単に偽造できる環境が整っていました。
さらに「まわりもやってるから…」という心理や、SNSで「申請代行します!」と呼びかける怪しい業者の存在も問題です。
制作会社として、できる注意喚起
私たちのようなWeb制作者・補助金サポート事業者にとっても、他人事ではありません。
クライアントに補助金の情報を提供したり、申請の相談を受けたりすることもあるからです。
そんなときこそ、以下のスタンスを忘れてはいけません。
- 適正な制度活用を促すこと
- 虚偽申請に加担しないこと
- 必要であれば専門家(税理士や社労士)を紹介すること
そして、少しでも「あれ?」と感じる相談があったら、慎重に距離を取ることも大切です。
まとめ:補助金は正しく使ってこそ意味がある
補助金・給付金は、困っている事業者を助けるための大切な制度です。
だからこそ、不正が横行すると、制度自体が見直されたり、信頼が失われてしまうリスクもあるのです。
私たち事業者は、「受け取れるものは受け取ろう」ではなく、「本当に必要な人が正しく受け取る仕組みを守る」という意識が求められています。
これからもクライアントの成長を応援する立場として、誠実で健全な制度活用を心がけたいですね。

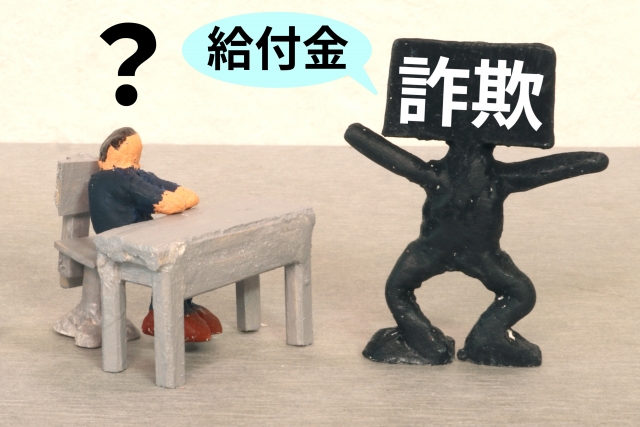
Comments are closed